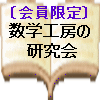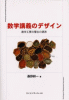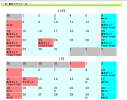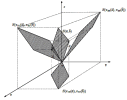| 数学工房 | Q&A お問い合わせ |
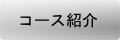
|
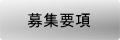
|
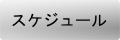
|
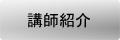
|
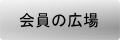
|
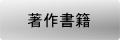
|
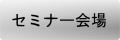
|
| 数学工房よりお知らせ | |
|
【10月20日の講座IC及びG 中止お知らせ】〔2024/10/18 15:30更新(掲載)〕 急ぎのご連絡です。 インフルエンザの感染による体調不良で、20日(日)の講座IC及びGは、現在の状況ではできそうにありません。 ・講座ICの振替日程について:(※メールより転載) 「『26日(土)13:30-15:30(作用素環研究会のあと)』あるいは『27日(日)10:30-12:30』のどちらかをお選びください。 絶対ダメな日程は特記してください。」 ご迷惑をおかけしますが、至急メールにてお返事ください。よろしくお願いいたします。 ・講座Gの振替日程について:27日(日)に延期させていただこうと思います。 ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。 数学工房 桑野耕一 |
|
|
【秋学期講座 日程変更のお知らせ】〔2024/10/7掲載〕 以下の通り、日程を変更させていただきます。 ・講座IB「複素関数論」……11/2 11/30 12/14 ・講座EC「局所コンパクトAbel群の解析学」……11/3 12/1 12/15 |
|
|
【数学工房の会費及び講座料について】〔2023/8/22掲載〕 数学工房では、会費及び講座料につきまして消費税をいただいておりません。 |
|
|
秋学期講座の情報はスケジュールページをご覧ください。 |
|
|
【2024年会費について】 2024年会費(1月〜12月) ¥3,000(学生 ¥1,500)を受け付けております。
集中セミナー、通常講座、研究会のご参加に必要です〔会費未納の方は受講できません〕。講座にご参加の方は、講座料と一緒にお振込みになるのが便利です。 会費は施設の維持や備品の費用の一部に使われます。ご協力をお願いします。 数学工房 ※お振込みの際には、「2024年会費」としてください。またお名前をお忘れなく。それ以前の未納分のある方は御一緒にお願いします。 ※数学工房の退会を希望される方は、連絡の上退会手続きをお願いします。 |
|
|
〔振込の場合の振込先〕 銀行口座:三井住友銀行 清瀬支店 普通預金 口座番号 4585253 数学工房 桑野耕一 郵便振替 00150−9−686515 数学工房 |
| 今週の講座 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||